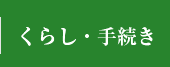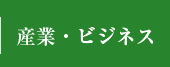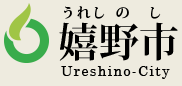温泉区面浮立保存会が九州大会に出演
令和2年11月8日(日)、中津文化会館(大分県中津市)にて開催された第62回九州地区民俗芸能大会に、佐賀県を代表して「嬉野町温泉区面浮立保存会」が出演されました。
九州各地の様々な伝統芸能のひとつとして、古くから嬉野に伝わる勇壮な面浮立の演技を披露していただきました。
温泉区面浮立の概要
「面浮立」は、佐賀県に伝承される民俗芸能です。
元亀元年[1570年]8月、豊後の大友親貞が、大軍を率いて肥前の国に攻め込んだ際、肥前の龍造寺隆信の客分であった鍋島平右エ門(後の鍋島直茂公)が、一族郎党に鬼の面をかぶせ「シャグマ」を付け、陣鉦、陣太鼓の音も勇ましく夜襲をかけて大友軍を破りました。その戦勝祝いの宴で、鍋島公が兵士たちにそのままのいでたちで躍らせたのが「面浮立」の起源と言われています。
現在では神事に用いられることが多く、県内各地で五穀豊穣、天下泰平、悪魔退散を祈って神社に奉納されています。
温泉区では、4年に1回、おくんちに地元の氏神様である豊玉姫神社にて奉納されます。
温泉区面浮立は、笛・大太鼓・鉦の囃子に合わせて、掛け打ち(踊り手)が『奉願道(ほうがんどう)』にて入場し、腰を低く落として、腕を振り、足をあげ、激しく体を動かす、とても勇壮な踊りです。
また、活動の一環として、後継者の育成の為に、地元の小中学生及び園児等に参加してもらい、郷土の芸能である「面浮立」を地域と一体となって継承できるように取り組んでいます。
TEL:0954-66-9320
FAX:0954-66-9321
MAIL:liberty-ureshino@po.hagakure.ne.jp