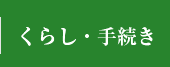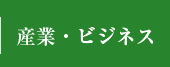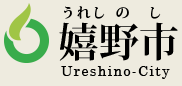嬉野市における食育の取り組み
笑顔はじける 健康うれし〜の!
嬉野市は、持続可能な社会の実現に向け「生涯にわたる心身の健康と豊かな人間性を育み、生きる力を身につけること」「食が自然の恩恵の上に成り立っていることや、食に関わる人々の手によって支えられていることの理解と感謝を深めること」を基本的な考えとして推進していきます。
目指すべき方向
-
食に関心を持ち、正しい知識を身につける
-
地域の人々と交流し、食育体験を行う
-
嬉野市の特産物や食文化を学び、次世代へ伝える
家庭における食育の推進
- 毎月19日(食育の日)は家族だんらんで食事を楽しむ
- 野菜料理を作り、毎食食べるよう心がける
- 家族と一緒に食卓を囲む機会を作る
- うれしの茶を飲む習慣をつける
地域における食育の推進
- 郷土料理や特産物を使った料理を次世代へ継承する
- 地域コミュニティを単位として地域と連携し「食の大切さと楽しさ」を習得できるように、学習会・講習会、講演会などを開催する
未就学児の保育施設における食育の推進
- 食事のマナー教室(食事前の手洗い、箸や茶わんの持ち方、食べ方、後かたづけ)を開催する
- 野菜の栽培、収穫、料理などの体験学習を推進する
学校における食育の推進
- 「子どもが作る弁当の日」を推進する
- 高校を卒業するまでに、簡単な料理を自分でつくることができるように体験学習をする
- 児童生徒及び保護者へ食育授業、試食会での講話など食育推進の啓発を行う
- お茶の入れ方を学習する
行政における食育の推進
- 市報やホームページ、行政放送等を利用し、食に関する情報を提供する
- 市民への栄養・健康相談、特定保健指導を実施する
食の安全と持続可能な食を支える食育の推進
- うれしの茶を毎日飲むことを推進する
- 生産者やJA等と連携し、お茶の摘み取りや製造などの体験、お茶の入れ方教室を普及する
- 保育園・幼稚園や学校で地元の生産者の協力を得て、農産物の栽培や収穫等の体験・交流会を実施する
関係者が連携した食育の推進
- 関係団体と協力して講師派遣の体制整備を図る
- 関係施設への食育ポスターの配布などによる普及啓発を行う
嬉野市健康総合計画では、食生活について、次のような内容を推進しています。
食生活の目標
★自分に見合う適量を食べて、適正体重を維持しよう
体重は、生活習慣病や健康状態との関連が強く、特に肥満はがんや循環器疾患、糖尿病等のリスクを高めます。また、若い女性のやせは骨量の減少や将来母体へ影響を及ぼすことが考えられます。また、高齢者のやせについては、心身の活力が低下し、日常生活に支障をきたす危険性が高くなります。まずは、それぞれが自分の適正体重を知り、自分に合った適切な量と質の食事をとることで、健康の維持・増進、生活習慣病予防を推進します。
★1日3食バランスよく食べよう
3食をバランスよく食べることは、必要な栄養素を摂ることはもちろん、心身を健康に保つために重要であり、乳幼児期、学童・思春期の食習慣は、青年期以降の食習慣にも影響を与えます。また、主食・主菜・副菜をそろえて食べることで、必要な栄養素を摂取でき、良い栄養状態につながることが期待できます。今後も、1日3食の食事をバランスよく食べることの大切さについて理解を深めることができるよう取り組んでいきます。
★朝食をしっかり食べよう
朝食は、脳へのエネルギー補給、血糖上昇、ホルモンの分泌、生活リズムの調整など、大切な役目があります。朝食の欠食は、食生活のリズムが乱れ、体調不良、肥満や生活習慣病への誘因になると考えられます。子どもの頃から、早寝・早起きで食べるための時間を確保し、朝食をしっかり食べるように推進します。
★脂肪・塩分・糖分を控え、野菜の摂取を増やそう
野菜には、ビタミン、ミネラル、食物繊維など体に必要な栄養素が豊富に含まれています。国では、1日の野菜摂取目標量を成人一人あたり5皿(350g)と設定しています。野菜摂取目標量について市民に周知し、今より一皿分多く野菜を摂ることを心がけることができるように取り組みを推進します。
★郷土食や食文化に関心をもち、次世代に食の大切さを伝えよう
食を取り巻く環境やライフスタイルの多様化によって郷土料理や伝統的な食文化が十分に継承されず、その特色が失われつつあります。
郷土料理や伝統食材、食事の作法等、伝統的な食文化に関する関心と理解を深め、次世代へ食の大切さを伝えていけるように関係機関や関係団体と連携して、子どもから高齢者まで生涯を通じた食育活動に取り組みます。
目標に向けた取り組み
市民一人ひとりの取り組み
妊娠期
- 妊娠期の食生活や、出産後の乳児の栄養などについて積極的に知識を身につけます。
- 妊娠期に必要な栄養バランスのとれた食事を心がけます。
乳幼児期(保護者)
- テレビを消して家族一緒の楽しい食事ができるように心がけます。
- おやつは補食と考え、時間や回数、量や質を見直します。
学童期
- 食事のバランスや食品に関心を持ち、食を選択する力を身につけます。
- 食事づくりを手伝い、食への感謝の気持ちを育みます。
思春期
- 食事づくりに取り組み、自分で食生活を管理できる力を身につけます。
青壮年期
- 外食時も、栄養バランスや塩分に気をつけた食事をします。
- 時間をかけてゆっくりと食事を楽しみます。
- 簡単でおいしく作れる調理法、加工食品や調理済み食品の上手な利用法を身につけます。
高齢期
- 1日3食栄養バランスを考えた食事をします。
- 低栄養にならないように十分なたんぱく質摂取を意識します。
- 郷土料理や伝統料理を次世代に引き継ぐ役割を積極的に担います。
全ライフステージ
- 食への感謝の気持ちを忘れず「いただきます」「ごちそうさまでした」のあいさつをします。
- 「早寝・早起き・朝ごはん」による規則正しい食生活を身につけます。
- 家族と一緒に食卓を囲む機会を作り、食事を通してコミュニケーションをとります。
- 自分の適正体重を知って、1日3食、主食・主菜・副菜がそろった食事をします。
- 1日の野菜摂取目標量を知り、野菜をたくさん食べる工夫をします。
- 薄味を心がけ、塩分の摂りすぎを防ぎます。
地域の取り組み
地域コミュニティ
- 世代間交流を図りながら、食の体験学習の機会を増やします。
食生活改善推進員
- 朝食の大切さを理解してもらうために、学習会を通してみそ玉つくりなど様々な取り組みを進めます。
- 地域や学校における食育を支援します。
- 短時間で簡単に用意できるバランスのとれたメニューや調理法などを提案し、普及します。
- 食事を作る力を身につけるための体験型教室を実施します。
行政の取り組み
情報発信
- ライフステージに合った食事について情報提供を行います。
- 野菜が多く摂れるレシピや栄養バランスのとれたレシピや栄養バランスのとれたレシピを提案し、普及・推進します。
- 市報やホームページ、うれしのホットステーション等を利用し、食に関する情報を発信します。
- 各年代に応じた食に関する教室を開催し、市民の食への関心を高めます。
学習や相談の場の提供
- 食に関するイベントや教室などを通して、生活習慣病予防のための知識を深める機会を増やします。
- 地域において積極的に食生活改善普及活動をする人材を養成します。
- 関係各課と連携して、食について知識を深め実践できる環境を整備します。